2025/04/17 09:03
亀甲文様は、伝統的な日本の文様のひとつで、読み方は、「きっこうもんよう」と呼ばれています。
長寿吉兆の象徴である亀の甲羅が由来となる、正六角形の幾何学模様で、長寿や繁栄、魔除けなどの意味があります。
吉祥文様(縁起が良いとされる模様や柄の総称)として親しまれており、着物や帯、陶器、甲冑などに用いられています。
亀甲文様は、長寿、繁栄、魔除けの意味があります。
まず、「鶴は千年、亀は万年」という言葉があるように、亀は古くから長寿の象徴とされています。
次に、正六角形が無限に広がる形が永遠の繁栄を意味しています。
さらに、亀の甲羅が身を守る形をしていることから、魔除けの意味もあります。
亀甲文様は、飛鳥時代から奈良時代にかけて、中国から日本に伝来したと言われています。
当時の中国は、亀ト(きぼく)(ウィキペディアによると甲卜(こうぼく)ともいいます)
という亀の甲羅に熱を加えて、生じたヒビの形状を見る占いが行われていました。
そのため、亀の甲羅を模した亀甲文様は、中国国内においては、とても神聖なものとして扱われていました。
その後、日本に伝来すると、中国国内と同様に“神聖な文様”として扱われることになります。
身分制度がだんだん厳格になると、亀甲文様は貴族のみが使用を許された文様となり、大変高貴な文様のため、一般庶民は見ることもなかったようです。
亀甲文様の正六角形は、自然界のなかで、もっとも安定性のある形といわれています。
NHKのサイエンスZEROでもやっていましたね。
正六角形の集合体は、“ハニカム構造”と呼ばれており、耐震性が重視される建築物などによく使われています。
そんな理由から、亀甲文様は“強い力”を意味するようになり、武士の間でもてはやされたようです
亀甲文様は、いくつかの派生文様があります。
代表的なものとしては、
正六角形を繋ぎ合わせた「亀甲繋ぎ」、
正六角形のなかに花弁が描かれた「亀甲花菱」、
正六角形を三つ組み合わせた「毘沙門亀甲」、
などがあります。
#工芸品
#切子
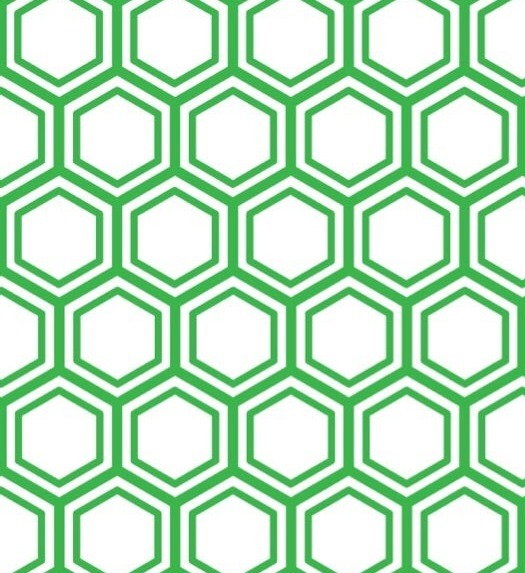
亀甲繋ぎ
--------------------
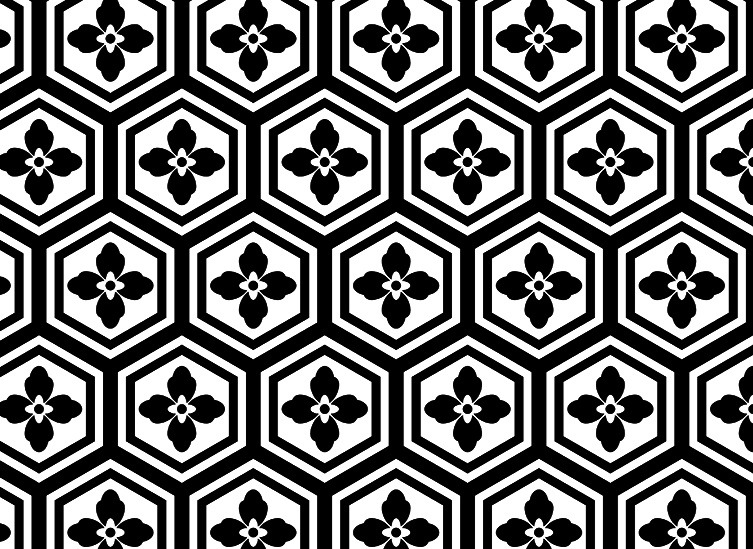
亀甲花菱
--------------------
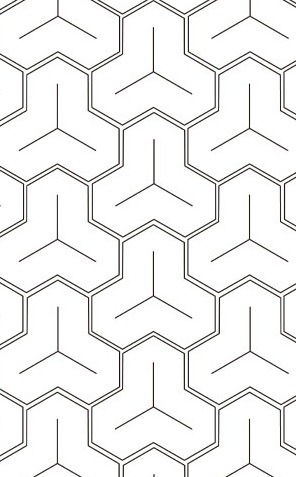
毘沙門亀甲
